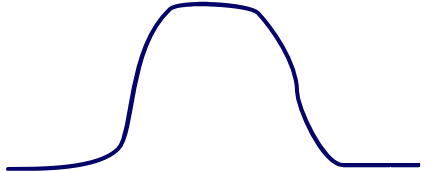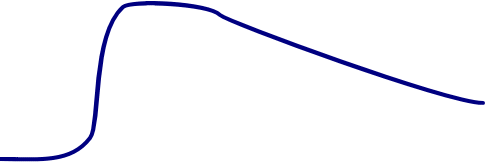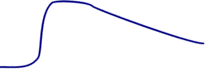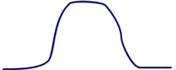本来身体をより適切な状態に持っていってくれるはずの自律神経が、症状の持続に関与するという状態になってしまっている場合は、意識的に自律神経のコントロールを試みることもあると、心と身体の関係-自律神経系-で述べました。
そのような具体的な方法としてリラクセーション法やバイオフィードバックなどがあります。自律神経系や筋緊張などの身体の状態をコントロールすることで、身体の状態をより適切な状態に保ち、本来のバランスを取り戻すことにつなげようというわけです。
◇リラクセーションとは◇
「リラクセーション」とは、本来は「弛緩」とか「緩和」という意味で、「緊張」に対する言葉です。つまり簡単に言えば身体や心を緩めることです。
「リラクセーション反応」(→BOOKSHELF)の著者であるハーバート・ベンソン博士は「闘争・逃走反応」に拮抗するのが「リラクセーション反応」であり、リラクセーション反応によって闘争・逃走反応を中和することができると述べています。
「闘争・逃走反応」というのは動物の世界での表現であって、秩序の整った?現代において「逃走」が必要という場面はそうそうありませんが、代わりに人間関係などから「緊張」を強いられる場面はよくあります。
ですから、「闘争・逃走反応」というのは、現代の生活で言えば緊張を強いられるようなときに生じる身体の反応のことと考えればよいでしょう。
例えば心拍数が増える、呼吸が浅く早くなる、瞳孔が開く、手に汗を握る、などです。これらは主には自律神経の中の、交感神経といわれるものの緊張が相対的に大きくなって起こる反応です。(交感神経と拮抗するのが副交感神経というもので、これはどちらかというと身体を休める方に作用する神経系です。)
このような身体の反応は、状況に対応する為に必要な反応であり、それ自体悪いものではありません。しかし、この緊張状態が日常的に続き、休息と比較して極端に大きかったり、休息すべきときにも緊張が続いたりするようになると歪みが生じて、いろんな身体症状や精神症状を引き起こすことがあります。
身体症状が持続した場合は心身症の状態になることもあります。精神症状としては不安障害やうつ、不眠などが代表的です。社会的な場面において過度の緊張が起こり、それがコントロールできないような状態は「社会不安障害」とか「対人緊張」と言われることもあります。そこで、過度に多くなった「緊張反応」を中和する「リラクセーション」が必要になってくるのです。
◇バランスとメリハリ
ただ、ここで一つ注意しておかなければならないことは、「心地よい緊張」というのもあるということです。「緊張」が悪くて「リラクセーション」が良いから「リラクセーション」の方に持っていこう、という単純なことではないのです。
緊張にもいろいろあり、リラクセーションにもいろいろあると考えられます。しかし、複雑な要素を考えていくと混乱してしまうので、わかりやすいように単純化して二つの反応として表現しています。
一番大切なことは「緊張」と「リラクセーション」のバランスとメリハリです。
緊張すべきときに適度に緊張し、休むべきときに適度にリラックスする。そのバランスとメリハリを自分でつける方法がリラクセーション法です。
自分でコントロールできる、ということが大事です。それには前提として自分の身体の状態を的確に知ることが必要です。緊張や弛緩の感覚が敏感な人もあれば、そうでない鈍感な人もあるでしょう。
心身症の患者さんにおいては、そのような感覚が健康な人に比べて敏感すぎたり鈍感すぎたりする傾向があることが分かってきています。
そのような感覚を適切なものにして、セルフコントロールを目指すのが、心身医学的なリラクセーション法です。様々なリラクセーションの方法がありますが、それぞれに長所と短所があり、自分に合った方法を見つけることが大切です。
リラクセーション法はその使い方が大事です。
リラクセーションの習得に熱心になってしまってかえって緊張がとれない、という笑い話のようなことが実際にはしばしばあるので注意しましょう。